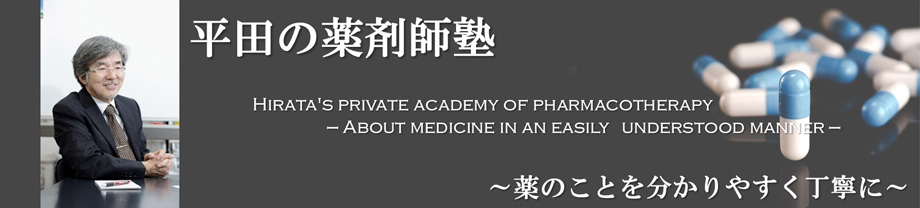わからないことが多すぎる
わからないことが多すぎる
なぜ、病院薬剤師が研究しなければならないか?それは「わからないことが多すぎるから」なのです。今私は、わからないことだらけです。今まで薬学部で学んだこと、多くの患者さんを今までに見てきたことから学んだこと、ドクターから学んだこと、多くの書物や文献から学んだことが本当のたくさんあります。でもわからないことはまだまだあります。今私が知りたいこと。私の病院は腎不全専門病院なので、腎不全患者さんについてのことが多いのですが、たとえば身近な薬のジゴキシンにだってたくさんあります。
- ジゴキシンの吸収は制酸剤で低下するけど、リン吸着剤の炭酸カルシウムで吸収は低下するのか?それは用量依存的か?
- 腎機能はCLCrで表すけど、ジゴキシンのように糸球体濾過されるだけではなくて尿細管分泌からも分泌される薬物の投与設計はCLCrによる計算式で適合できるのか?そして透析患者の尿細管分泌は無視できる量なのか?
- ジゴキシンの相互作用は多く、ベラパミル、キニジンなどはジゴキシンの腎排泄を阻害するといわれているけど、それだったら腎機能の廃絶した透析患者ではそのような相互作用は起こらないはず。でも実際には起こっているのはなぜなのか?
- 透析患者ではジギタリス様免疫反応物質が血中に存在するために測定誤差が生じやすいが、ジギタリス様免疫反応物質はどのような病態で発現するのか?
別にこれらの疑問は実験室に入って試験管を振らなければできないようなテーマばかりではありません。TDMの測定データと患者背景を詳しく調べることから解明されることも多いのです。
「研究はやりたいけれどテーマがない」なんて行っている薬剤師はいないでしょうか?私は逆です。「わからないことが多すぎる」のです。身近な薬の中にも、わからないことはたくさんありますし、おそらく、上記の疑問は自分で答えを探さなくては、誰も答えてはくれません。だから研究するのです。薬剤師は何のために必要なのか?薬剤師のアイデンティティは何なのか?を考えてみてください。単に薬剤を管理し、調剤するだけなら、今まで学んできた「薬学」は何のためにあったのでしょうか?単に薬剤を管理し、調剤するだけなら、専門学校でも十分教えることができます。4年間学び、そしてこれから先、6年間学ぶ必要があるということに現場の薬剤師からはほとんど異論がでてこないのに、現場の薬剤師が薬学を活用しきっていまい現実は何なのでしょうか?薬学をベースにして調剤すれば、この薬はこの病態の患者にこの量でよいのだろうか?という疑問は必ず生じてくるはずです。そして疑問が生じたら調べるはずです。そして調べてもわからなければ自ら解明しなければ誰が答えてくれるでしょう。薬剤師は薬のプロフェッショナルのはず。この先、6年間勉強してきた薬剤師に教えなくても薬剤師の存在価値を示すことができるような職場に変えていく必要があるとは思いませんか?
Yes, we canの輪を広げよう
“Yes, we can” の輪を広げよう
「えー?学会で発表なんて!」なんて思っている人はいませんか?今までに薬局の先輩達が一度も発表したことがない方はそう思うかもしれません。でも、我々、白鷺病院の薬剤師であれば学会発表は必須の仕事、学会発表することが当たり前になっていますから、どの薬剤師も決して「自分にはできない」とは言いません。私自身が学生時代、相当の劣等生でしたが、そんな私にでもできているのだから、若い薬剤師達も「君にだってできないはずがない」と励ますことはありますが、みんながやっていれば誰でもできてしまうのです。結局、学会活動の活発な薬剤師の多い病院とそうでない薬剤師の多い病院の違いは「私にでもできる」「私にだってできないはずはない」と考えるような土壌ができているかどうかの違いではないでしょうか?決して我々は競って発表しているわけではありません。薬局内の勉強会で疑問に残ったテーマ、解決できていない問題症例を何とか文献検索して、あるいは薬剤師同志で話し合って、あるいは医師やナースなどと話し合って疑問を解決したいと思うのはプロの薬剤師として当然のことだと思っているのです。解決できていない薬の問題点や症例に対する疑問点を全精力を注いで解決し、一定の結論が得られれば、それがポジティブデータであっても、ネガティブデータであっても学会発表、文献執筆という形で報告することによって完結させます。学会でフロアーや座長から質問さしていただくことによって、あるいは文献投稿時にレフェリーに批判していただくことによって薬剤師として、そして研究者として一歩一歩ステップアップしていくものだと思います。「私はちゃんと学会発表していますよ」なんて、地方の研究会程度で満足していませんか?ステップアップするための階段はまだまだあるのですよ。とはいえ人間が成長して大きくなることは決してたやすくありません。結局、少しずつステップアップするしかないのです。薬剤科内の症例検討会→院内の症例検討会(薬剤師も院内の症例検討会に参加して、薬剤師も症例報告しています)→地方の学会発表→全国レベルの学会発表→文献投稿→国際学会発表→英文文献の投稿→国際的に認められた一流紙への投稿、このようにあなたの成長する余地ははまだまだあるのです。一段一段上がるごとに薬剤師として大きく成長しているのが自分で体感でき、数年前の自分がどんなに低いところにとどまっていたかがわかると思います。勉強はちゃんとしていても、学会でちゃんと話を聞いていても、あなたは高い山を見上げているだけ。見上げているだけでは全然、頂上には近づかないのです。周りの人が登り出さないのなら、あなた自信がステップを踏み出してみてください。学会で質問され、あるいは文献投稿時にレフェリーに批判されるのを恐れてはいけません。我慢強くやれば、いい仕事はきっと評価されます。リサーチマインドのない薬剤師の集まりでは他の医療スタッフから評価されるはずはありませんし、社会的評価も得られません。「私だってできるのです(Yes, I can.)」、あなたのこの考え方がyes, we can”の輪になって広がってゆけば薬局全体に活気がみなぎることは間違いありません。
Pharmacist dilemma
薬剤師は学校でかなり難しいことを習います。そして卒後も実によく勉強します。薬剤師会やメーカーが勉強会を開催すれば多くの薬剤師が集まりますが、これは医師を除く他の医療職種にはない現象だと思います。しかしこれらが十分、臨床に生かされているとは言い難いのです。学校で習った知識が一番生かされていない医療職種は薬剤師ではないでしょうか。これに関して反論する方も多いとは思うが、現在の多くの薬剤師は薬学で得た化学的知識を仕事に十分生かしているでしょうか?薬物動態学や薬理学、生化学で得た知識を臨床に十分に生かしているでしょうか?全く生かされていないとは思いませんが、どれも断片的なものであり、難しいことを学びながらもそれらを仕事に十分生かせないと思います。「この仕事はやっぱり薬剤師でなくては」といわれるような仕事をできていないこと、これを私はpharmacist dilemmaと名付けたいと思います。ジレンマとはあちらが立てばこちらが立たず、ということです。この問題になると多くの薬剤師は大学教育の問題と決めつける方が多いのです。確かにそれもあるでしょうが、医療現場での教育システムの欠如、リサーチマインドを持つ薬剤師が非常に少ないことの方が大きな問題ではないかと私は考えます。
リサーチマインドのない薬剤師が病院から評価されるわけはありませんし、社会的評価も低くなった薬剤師になろうと思う学生は減り、薬剤師のレベルはさらに低下すると考えられます。
しかし一方で、病院薬剤師が外来調剤中心から病棟での服薬指導中心の業務になってから、見違えるように大きくなった薬剤師が散見されつつあります。大学病院の先生方は、以前から多くの業績を残しているため除くとしても、一般病院でもTDMに関しては国立循環器病院の上野和行先生、薬物アレルギーに関しては新潟水原郷病院の宇野勝次先生、そして若手ではEBMに基づく薬剤師業務を推進する愛知厚生病院の三浦崇則先生、科学的な副作用モニタリングを実践している中国労災病院の前田頼信先生などなど、「薬剤師でないとできない業務」を遂行している薬剤師が現れはじめました。これらのひと味違う薬剤師は結局、自分自身のアイデンティティを持ち、「自分からイニシアチブをもって仕事のできる人」であり、安全かつ有効な薬物療法を患者に提供できる薬剤師だと思うのです。今までの薬剤師は医師の指示通り、処方箋に従って調剤をするという行為に慣れすぎたのではないのでしょうか?病院薬剤師の定員削減が話題になる中で、調剤技術だけでない「本当に病院にとって必要な、幅広い臨床的技能を身につけた薬剤師」の養成がこれからの重要課題になると思われます。そのためにはいつまでもorder takerであってはなりません。これからの薬剤師はself starter(自分からイニシアチブをもって仕事のできる人)に変貌する必要があります。