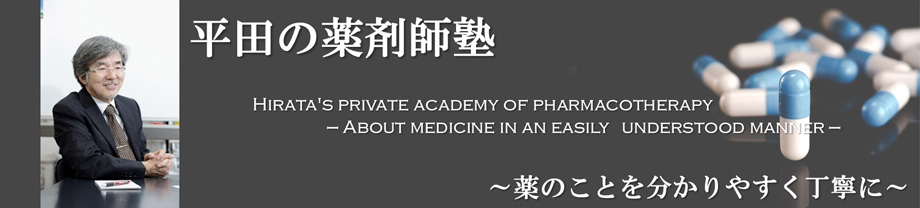★◆連載◆27日目 発汗によって脱水になったら、どうやって水分の喪失を防ぐ?
腎の構造と機能から学ぶCKDの病態
27日目 発汗によって脱水になったら、
どうやって水分の喪失を防ぐ?
~ADHとアルドステロン、ANP/BNPの違い~
尿量は最終的に集合管で決められる。脱水にならないための主役は昇圧系の代償機構の代表であるRAASのアルドステロンとともに、抗利尿ホルモンADHで、これらが尿量を減らすことによって脱水を防いでくれている。ついでに言っておくと、降圧系の代償機構の代表であるANP(心房性Na利尿ペプチド)やBNP(脳性Na利尿ペプチドだが実際には心室で分泌されている)は心房・心室から分泌され、集合管でのNa再吸収を抑制している(図1)。これはANPやBNPの分解を阻害するサクビトリル/バルサルタンというアンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)の快進撃によって心・腎保護作用が注目されている。 この続きは登録ユーザーのみ閲覧できます
★◆連載◆26日目 アルドステロン分泌異常疾患、ADHの分泌異常疾患による血清Na値異常
腎の構造と機能から学ぶCKDの病態
26日目 アルドステロン分泌異常疾患、
ADHの分泌異常疾患による血清Na値異常
高ナトリウム血症と低ナトリウム血症
血清Na濃度の正常値は135-145mEq/Lだが、症状は120 mEq/L未満、あるいは160 mEq/L以上になってから起こる。高ナトリウム血症と低ナトリウム血症の症状はよく似ている。「どちらも悪心・嘔吐、倦怠感、意識障害、痙攣と覚えよう。高ナトリウム血症になって意識障害を起こしたのか、低ナトリウム血症になって意識障害を起こしたのかは患者の原因疾患やシチュエーションを見ればわかる。」と熊本大学の学生には教えていた(図1)。 この続きは登録ユーザーのみ閲覧できます
第31回 基礎から学ぶ薬剤師塾 Q&A
第 31回 基礎から学ぶ薬剤師塾 Q&A
初心者向けシリーズ③糖尿病性腎臓病とその治療薬
2023年11月17日アンケートによる質問
氏名を書いていただきましたが、匿名とさせていただきます(批判的な回答をしましたので)。
Q1 .SGLT2の腎機能低下例への投与について、先日eGFR30を下回ってる患者への投与で薬効が期待出来ないとの事から疑義をしましたが、投与するという回答でした。本日のご講演から20を下回らなければ投与に意義があると考えていいのでしょうか。
A.「薬効が期待出来ない」からで考え方は合っています。たしかにSGLT2阻害薬を腎機能低下例に投与すると腎に作用する薬ですから効きにくくなりますが、メトホルミンのように乳酸アシドーシスという致死性副作用を起こしたりNSAIDsのように薬剤性腎障害で透析導入などのリスクが高くなるわけではありませんので、個人的には透析導入になるまで、疑義照会せず、見守っていいんじゃないかと思います。
SGLT2阻害薬の添付文書には「 重度の腎機能障害のある患者又は透析中の末期腎不全患者では本剤の血糖降下作用が期待できないため、投与しないこと」となっています。重度というのは一般的にeGFR30 mL/min/1.73m2未満のことですが、この添付文書はおそらく発売当初から書かれた内容だと思いますが、添付文書はよほどのことがない限り、書き直されることはありません。しかしその後の臨床試験はそれより低い腎機能の患者を対象にしたものもあり、それによって各国の学会の指標も変わりつつあります。
厳密に言うとエンパグリフロジンのRCT試験はeGFR20 mL/min/1.73m2以上を対象とした試験があるため、20以上あれば投与開始できます。ダパグリフロジンのRCT試験はeGFR25以上を対象としているため、25以上あれば投与開始できます。カナグリフロジンはeGFR30以上のDM患者のみを対象としています。それ以外のSGLT2阻害薬はDM患者のみを対象としており、心不全やCKD患者に対する試験は行われていません。⽇本腎臓学会 のCKD 治療におけるSGLT2 阻害薬の適正使用に関するrecommendationでは要約すると以下のことが明記されています。
①糖尿病合併 CKD においては eGFR20 mL/min/1.73m2 以上であれば,クリニカルエビデンスを有する SGLT2 阻害薬の 積極的な投与開始を検討すべき。
②eGFR15mL/min/1.73m2未満では新規に開始すべきではない。
③SGLT2 阻害薬開始後に eGFR15 mL/min/1.73m2未満となった場合には,副作⽤に注意しながら継続する。
だから平田は添付文書通りに「eGFR30mL/min/1.73m2未満の患者さんには禁忌です」という型にはまったような疑義紹介をするデジタル薬剤師にはなってほしくないと思っています。
開始基準は上記の試験の通りですが、患者さんに不都合が生じないのであれば、いったん開始したSGLT2阻害薬を透析導入までは続けてもいいと思います。SGLT2 阻害薬が腎機能が落ちてもある程度効果があるのはなぜなのかについては明確にされていないし、どこまで効くかもよくわかっていないからです。
ですから多面的な薬理作用と強力な腎保護作用を持つSGLT2阻害薬ですから、添付文書に記載されたよりも低い腎機能低下患者への治療効果の可能性を確認したい医師がいれば、薬剤師としては一緒になって副作用が起こらないようサポートし、効果が得られるかどうかを見守ってみてもいいんじゃないかなと思っています。
Q2 .SGLT2阻害薬が投与されている患者さんへの説明の中で、「食事ができないときには、服用しないように。」と伝えていますが、「どれくらい食べられたら飲んでも良いですか?」と聞かれます。食べられないのが単回の事であれば、パン1個とか、おにぎり1個程度食べたら、服用しても大丈夫なのでしょうか?目安等があれば、お教えください。
A.「食事ができないときには、服用しないように。」は良い指導だとは思いますが、実はSGLT2阻害薬を1日、服用をやめても尿糖は出続けます。おそらく数日間(1週間以内)、尿糖排泄は持続しますので、しばらくはグルカゴン/インスリン比が上がり、脂肪が分解されケトン体の産生する状況が持続すると思います。
ですから「この薬を服用する場合には全く炭水化物を摂らないような厳格な糖質制限食や、極端な低カロリー食はやめてください(ケトン体の産生が亢進しますので)。毎食、少しのご飯かパン(ジャガイモやカボチャなどがおかずに入っているだけでもいい)を摂るようにしてください。でないとケトン体産生が亢進しすぎると脱水になって、嘔気・嘔吐、腹痛、意識障害の激しい症状(ケトアシドーシス)が起こることがあります」という指導の方がよいように思います。目安としては「少しのご飯かパン(炭水化物)を必ず摂るように」(炭水化物を多く摂りすぎると血糖値が上がるのでインスリン分泌が増え、SGLT2阻害薬の薬理作用が期待できなくなる)でいいと思います。
Q3.1型糖尿病患者へのSGLT2阻害薬処方時にケトン体測定チップをお渡ししようと思いますが、その他1型糖尿病への特別な注意点があれば、ご教示ください。
A.1型糖尿病患者さんはインスリン依存状態なので、2型に比べて極めてケトアシドーシスになりやすいので、ケトン体測定チップをお渡しすることはとても良いことだと思いますが、自己測定によるケトン体測定について僕はあまり知りません。ごめんなさい。
ただ調べてみると、結構、測定法によって正確性にばらつきがあるようで、病院で測定する正確な静脈血中βヒドロキシ酪酸濃度に近くなるような直接的に毛細血管中のβヒドロキシ酪酸を測定するものがいいようです(PMID: 18637083)。
★◆連載◆25日目 フロセミドは浮腫改善作用を持つ利尿薬であり、サイアザイドは利尿降圧薬
腎の構造と機能から学ぶCKDの病態
25日目 フロセミドは浮腫改善作用を持つ利尿薬であり、
サイアザイドは利尿降圧薬
フロセミドは浮腫改善薬であって長時間作用型ループ利尿薬とは異なる
ループ利尿薬の中のフロセミドだけは半減期がほぼ1時間以内と非常に短いので、まさにフロセミドこそ「利尿薬」という名にふさわしいと思う。フロセミドの場合、細胞外液量は治療開始後数日の間に失われたナトリウムの量だけ減少したままである。サイアザイド系利尿薬では、最初の塩分と水分の喪失の後、一般的に塩分と水分の平衡が一定期間保たれ、細胞外液量が基礎値に近く(ただし、基礎値には達しない)戻る。この二次的な反応のメカニズムは明らかではないが、ループ利尿薬によるヘンレループからのNaCl排出量の増加は、遠位尿細管と皮質尿細管の肥大とNa再吸収能の増加につながることが示されているが、サイアザイド系利尿薬では、排出量の増加とそれに続く肥大反応は皮質尿細管に限られると考えられている。 この続きは登録ユーザーのみ閲覧できます
第32回 基礎から学ぶ薬剤師塾 お申し込み方法
第32回の「基礎から学ぶ薬剤師塾」は2024年1月19日(金)18時半から(20時半までの予定)です。今回は事情があり(平田は3月末まで日本にいません)、録画を見ていただき、Q&Aはございません。登録していただいた方のみ視聴できますが、再放送もございません。申し訳ありません。
今回のテーマは初心者向けシリーズ第4回目で、「初心者向けシリーズ④ 降圧薬を極める」です。大学で学んだ薬物治療学ではわかりにくかった高血圧の病態と降圧療法について、できるだけ分かりやすく解説したいと思っています。
参加を希望される方は 申し込みフォーム に記入のうえ、1月14日までに送信してください。
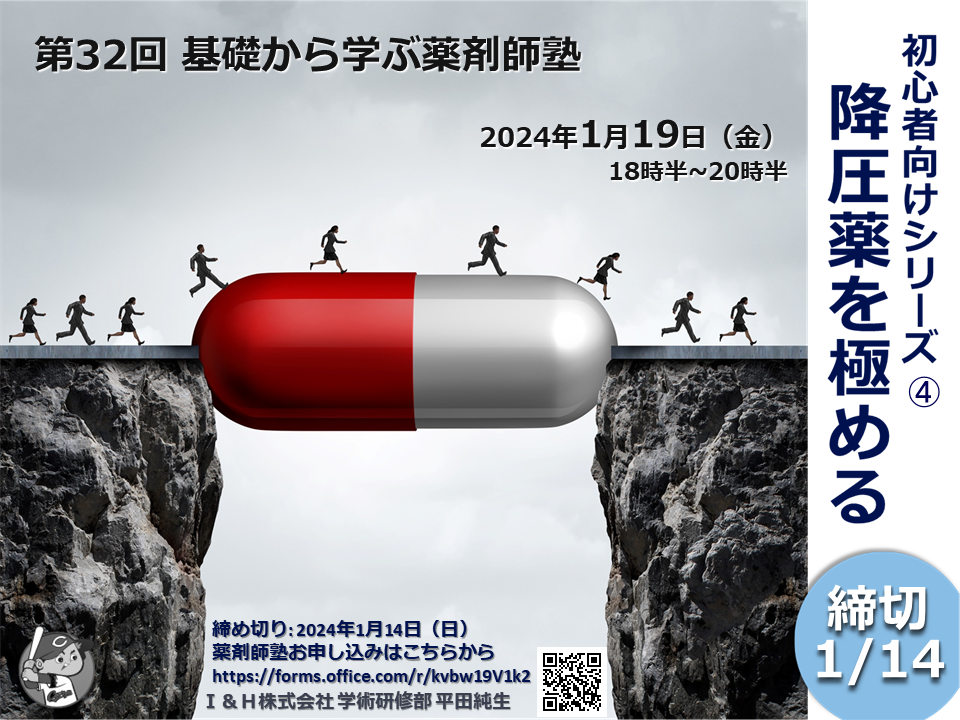
薬剤師塾となっていますが、医師・看護師など医療従事者であれば参加可能です。300名まで参加可能ですが、登録者数はいつも200名を超えていますので、早めに登録してください。
★◆連載◆24日目 サイアザイド系利尿薬再び
腎の構造と機能から学ぶCKDの病態
24日目 サイアザイド系利尿薬再び
話をサイアザイドに戻そう。
サイアザイド系利尿薬のタンパク結合率はフロセミドほどは高くないが、おそらく尿中排泄性薬物で、効果を発揮するには腎尿細管の内腔に到達しなければならない。この過程は近位尿細管の有機アニオントランスポータによって媒介される。したがって、腎機能が低下している場合には、より多くの利尿薬を尿中に排出するために投与量を増やさなければならない。腎不全患者では効果が乏しくなるのであまり使われない。 この続きは登録ユーザーのみ閲覧できます
★◆連載◆23日目 利尿薬について誤解していない?
- 22日目で泊まっていた連載ですが、実は日本腎臓病薬物療法学会、日本医療薬学会での講演、シンポジウム、臨床検査誌からの総説依頼のために休ませていただいておりました。本日より「腎の構造と機能から学ぶCKDの病態」を再開させていただきます。
腎の構造と機能から学ぶCKDの病態
23日目 利尿薬について誤解していない?
利尿薬への誤解~利尿作用は1~2週程度しか続かない?~
ナトリウム利尿薬について解説したい。すべて尿細管に作用して尿量を増やす薬だ。15日目、16日目にMRA、19日目に水利尿薬トルバプタン、21日目にARNIについて解説したので、今回は肝腎のサイアザイド系利尿薬・ループ利尿薬の本流の利尿薬について解説しよう。大まかにすべての種類の利尿薬の尿細管での作用部位について簡潔にまとめると図1のようになる。 この続きは登録ユーザーのみ閲覧できます
いつまで僕は走り続けるの? ー後編ー
マラソンは長い。僕らの年齢では4時間以上、ずっと心拍数160で走り続ける過酷なレースだ。そして30kmを超えると脚と足の全ての関節が痛む。だけどどんなに長くてもゴールはあるし、走り続ければそのゴールに近づく。そして長かった分、感じることのできる完走後の達成感。このために僕は数か月間、休むことなく走り続けたんだよ。土日は必ず20-30kmのLSD(これは幻覚剤じゃなくってLong, Slow, Distanceの略でゆっくり長距離を走るスタミナ練習、僕はこの時間を無駄にしたくはないので走りながらイヤホンで英会話や医学・薬学英単語を繰り返して聞いている)をやったんだよ。坂道ダッシュやペース走も、こんな年で無理してやったんだよ。食べたいものは我慢して炭水化物制限ダイエットを2か月近く続けてレースのために体重を5kgも落としたんだよ。だけど順位なんてどうでもいい。「やり遂げた」という気持ちを味わいたいから。この年になってもこのきついフルマラソンを完走できたんだということを心の支えにしたい。これは普段の生活や仕事にも当てはまる。嫌だけどやらなきゃいけないことが目の前にたくさんある。それから逃げるんじゃなく、工夫してうまく向き合い、何とか超えてゆくんだ。同じじゃないかな、スポーツも仕事も。レースの結果が悪くってもいい。苦しい練習を積んだんだというプロセスを大切にしたい。今回の結果がよくなくても今後の自分の成長にきっと役立つから。
きつい練習だけど、外に出るといつも神戸の穏やかな海が見え、振り向けば六甲山が見える。日本全国、旅をしながら旅先の景色を見ながらのランニングもとても気持ちいいし、その後のお風呂やサウナは最高だ。膝が治って69歳になってもなお、健康で走れるという喜びは何にも代えがたい。「目指せ大阪マラソン市民アスリート(1,500人)」という枠が大阪マラソンにはあって40歳未満の若い人はサブスリー、60歳代は3時間50分以内、そして70歳以上では4時間30分以内で走れば先着順で抽選しなくても走れるらしい。これを目指したい。だから70歳になってもマラソンはやめられないね。
学会に参加するといつも熊本のランニング仲間が声をかけてくれる。「日曜日の朝6時集合で走りましょ」。今年も10月の日腎薬名古屋大会では名古屋城まで仲間と走り、11月の医療薬学会仙台大会では青葉城まで仲間と走って朝焼けを見た。職場にはI&Hランナーズというランニングクラブがあって、定期的に長居公園や淀川河川敷での駅伝やリレーマラソンに参加する。距離は3-5kmなので、いつもよりハイペースの5分/kmと僕にとってはかなりのハイペースなので死にそうなきつさ。でも走った後には居酒屋でビールで乾杯!あ~、もう、最高!生きててよかった。

ということで2023年11月19日の神戸マラソンは60歳代で4時間25分19秒(平均ペース6分12秒/km)でした(写真)。去年の神戸マラソンより22分速く、9月の網走オホーツクマラソンよりも10分速く走れました。いつもは65kgある体重を59kgに絞ったのでやつれて見えますが、中身は元気です。
6分/kmで走り続ければ4時間13分、5分40秒/kmで走れば4時間の壁を超えられる。70歳で4時間の壁を超えられれば、本当にすごいと思う。
いつまで僕は走り続けるの? ー前編ー
あれは小学校の3年か4年の時だった。体育の時間に50m走の初めてのタイムを取った。僕は足が遅く、運動神経もとても鈍いので嫌だったけど、全員、1人ずつタイムを取った。結果は11秒で、女子で一番遅い子と同じタイムだったので、恥ずかしくて死にそうだった。すごく嫌な思い出だったし、小学校からや高校になるまで運動会やクラスマッチなどが大嫌いだった。できることなら学校を休みたかったが、そんなことのできる時代ではなかった。中学の3年間、僕は宮原1丁目に住んでいたので、中学のある13丁目まで歩いていかねばならず、重い革のカバンを持って、よれよれになりながら通学していたことを思いだす。高校の3年間は人前で話をすることが全くできない、女子と話をすることなんて全くない暗い学生時代を送っていた。
でも中学時代の遠距離通学がよかったのか、中距離や長距離は早くはなかったが人並みに走ることができるようになった。

運動神経が極めて鈍い僕が人並みにできるスポーツなんてないと思ってたけど、人並みに走れたのがただひとつ長距離走だったから、薬剤師になってから白鷺病院の仲間と、マラソンに参加するようになった。初めてのマラソンは4時間くらいかかり歩きもしたけど、フルマラソンは練習を積むと3時間20分台ではいつでも走れるようになった。28歳の時には3時間20分を切ることができた(写真)。目指すはサブスリー、3時間切りだったけれど、左ひざの故障、股関節(今から思うと大殿筋痛)の故障で走れなくなった。もうそろそろいいだろうと30歳代、40歳代とフルマラソンにエントリーしたが膝が痛くてリタイアするか、最後まで歩くと6時間以上かかった。もう一生、フルは走れないんだなと思った。2012年、熊本市が政令指定都市になったのを記念して僕が59歳、熊本大学教授の時に第1回熊本城マラソンが開催された。「走ってみたい・・・・。」でも左膝は数km走っただけで、痛む。熊本城マラソンの制限時間は7時間だ。時速7kmで歩けば6時間でゴールできる。来る日も来る日も時速7kmの早歩きの練習をした。そして2016年2月、61歳の時、6時間2分で完走ではなく完歩した。この時から毎年熊本城マラソンに毎年参加、膝が痛くなるまではゆっくり走り、痛くなったら歩くというスタイルで徐々にタイムがよくなり順位も60歳代では平均より上になってきた。そして2020年、コロナ禍の直前の2月、豪雨の中、靴が水浸しになって豆がつぶれそうになったため、妻に30km地点に靴を持って来てもらい履き替えたロスがあった。熊本城の最後の坂はいつものように心が折れて歩いしまったが、5時間16分でゴール。
2020年3月に神戸に引っ越してから、通っているジムで、フルを2時間30分以内で走るランナーのKさんにパーソナルトレーナーをお願いした。教わることはとても貴重なものばかりだった。まずはフォームの矯正をしていただいた。
①猫背にならないよう
②1秒間3歩のピッチで
③足趾で地面をつかむイメージで
④脚を高く上げるとストライドが伸びる
⑤腕を強く振る(というより強く引く感じ)
⑥顎を引く
⑦レースの時は塩熱サプリを摂る
これによって7分/km でもひーひー言ってたのが、不思議と6分/kmより速く走っても全然きつくない、おそらく省エネ走法が身に着いたのだと思う。そして68歳での神戸マラソンでは全く歩くことなく4時間42分でゴール。マラソンはいかにエネルギーをロスしないよう、少しずつアウトプットしていくのが大事。だからランナーズハイになって気持ちよくなる5-10kmでのスピードの出しすぎに気を付けた。そして最初はゆっくり6分40秒/kmでそれ以上早くならないよう我慢、そして25から30kmから意識的にパワーアップして、40km以降は腕の振りでスピードダウンを防いで最後までほぼイーブンペースで走った。
でも翌年2月の大阪マラソンはたっぷり練習を積んで絶好調だったが、頑張りすぎて左ふくらはぎの肉離れが起こり、無念のリタイア。僕は左脚が右脚に比べて明らかに筋肉量が少ないし、体幹が弱いのですぐに転びそうになる。体幹を鍛えるにはトレッキングがいいと聞いて、芦屋川から六甲山山頂を通る有馬までの11kmのコースを何度も登った。そしてKトレーナーから太ももだけではなく背筋、腹筋、上腕の筋トレで体幹を強化して、けがをしないためのストレッチを学んだ。69歳になって臨んだ今年の9月末の網走・オホーツクマラソンでは夏の間の練習不足があったうえに、最初の15kmまで標高100mのアップダウンが続く難コースだったが、タイムよりも完走が目標だったので、少し冒険した。最初の難所はランナーズハイになって、6分/kmのハイペースで貯金した。案の定、後半はばてたけど、60歳台でのマラソン再開後の最高の4時間34分でゴールできた。60歳代では266人中89位、全体でも1447人中696位で平均より上になった。これは運動神経の鈍い僕にとっては奇跡的な成績だ。
平田の独り言5
平田の考える薬剤師の定義は

有効かつ安全で
目の前の患者さんに配慮した最高の薬物療法を
責任もって提供する人
その前にすべての医療人に必須なものは患者さんに対する「やさしさ」だと思う。